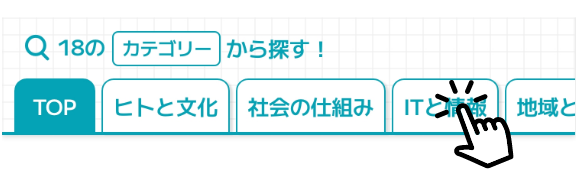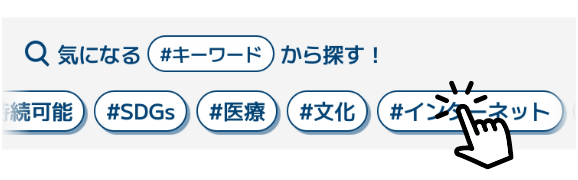この記事のカテゴリー
この記事でわかること
国際基督教大学のキャンパスには、武蔵野の原風景を残す広大な「ICU三鷹キャンパスの森」があります。絶滅危惧種を含む動植物が多数生息し、環境省の「自然共生サイト」にも認定されている、教育と実験・研究のエリアです。さまざまなプロジェクトが展開されていて、森の中を見て歩く「ICU生物多様性ウォーク」では、人の手で管理しているエリアの自然のバランスの良さを学生たちが実感しました。生態系については「自然に任せれば勝手に直してくれる」という考えが根強いですが、人間が崩してしまったら、人間が手伝わないと戻っていかないのです。
※出典:株式会社栄美通信 2024年8月発行「大学×SDGs」
絶滅危惧種を含む多様な動植物が生息
国際基督教大学(ICU)のキャンパス(東京都三鷹市)には、武蔵野の原風景を残す広大な森が広がっています。絶滅危惧種を含む動植物が多数生息・生育し、環境省の「自然共生サイト」にも認定された「ICU三鷹キャンパスの森」(約62万m2)です。
ここは武蔵野台地という扇状地の端に位置し、縄文時代から人が住み、江戸時代は農家の人たちが日常の資源を採取するなど、連綿と人の生活が在った里山。ICU献学後も、自然科学から人文、社会科学の分野まで関わりながら、この地の自然に対応してきました。
研究と気づきの宝庫
森は教育と実験・研究のエリアですので、日々いろいろなプロジェクトが学生主体で展開されています。僕の研究分野では、農家さんと堆肥づくりをしたり、養蜂に取り組んだりしています。また、湧水を利用して江戸時代に採れていたワサビを復活させようともしています。
2023年は「ICU生物多様性ウォーク」を開催しました。森の中を見たことのない学生を集めて僕が案内したのですが、みなさん普段見たことのない自然にとても喜んでいました。森は人の手で管理しているエリアと山に帰した場所とに分かれていて、その対比をしながら歩いたところ、「すごいね、この笹の量!」「こっちは蔦が山ほどあるけど、あっちは奥まで見通せるんだ」など、人の手が入ることでどれだけ変わるかを感じてもらうことができました。
人間が壊した自然は、人間が手伝わないと戻らない
普通は原生林の方が自然の多様性が高いと言われます。しかし、日本の場合は人の手が入っている方が高く、二次林の方が多様性が上回っているという紀伊半島のデータが発表されて世界中が驚きました。自然保護=自然に手を出してはいけない、ではないのです。人の手でゆっくりと維持しながら自然のバランスを取ることで多様性を高めることも可能なのです。
三鷹キャンパスの森では、冬になると近隣の農家さんたちが落ち葉掻きをします。地表に光が届くため、春にラン類など貴重な植物も芽吹いていますが、逆に人の手が入らなければ森は暗くなり、草木が出なくなります。生態系については「自然に任せれば勝手に直してくれる」という考えが根強いですが、人間が崩してしまったら、人間が手伝わないと戻っていかないのです。
文理を融合させた考え方で包括的に物事を見る
僕は、技術と知識が融合すれば、自然とのバランスを取ることは可能だと思っています。全部自然である必要もないし、全部人工である必要もない。そのためには型にはまらずに包括的に物事を見ることが大事で、文理を融合させた柔らかい考え方を持って欲しいと思っています。